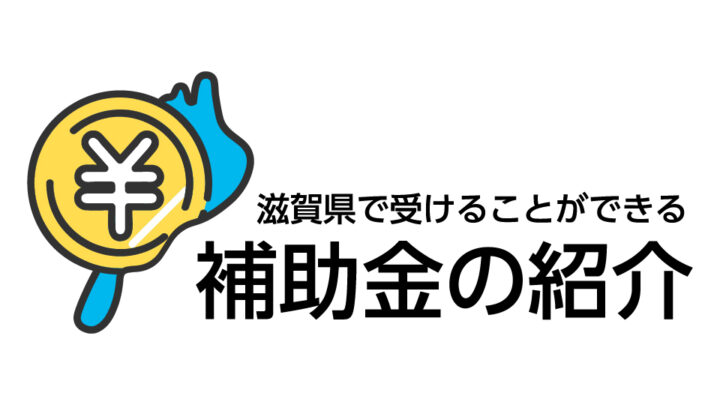【毎日新聞(滋賀版)】「工房シーダーノ」を紹介する記事が掲載されました
- 公開日
工房シーダーノ
2024/6/5 毎日新聞(滋賀版)

初夏の収穫期を迎えた六条大麦の黄金色の穂が、きらきらとなびく風景をあちこちで目にする滋賀県は、その生産量が全国高位の地域です。「魚のゆりかご水田プロジェクト」を推進している野洲市須原の「せせらぎの里」で、農薬・化学肥料不使用の六条大麦を栽培し、その茎で作ったストローをきっかけに環境問題への取り組みを広げている「工房シーダーノ」の八尋由佳さんを訪ねました。
自然や生き物が好きで、かつての朽木村(現 高島市)での自然観察の指導員や、大学や琵琶湖博物館での昆虫の標本作製などの仕事を続けてきた八尋さんは、2018年、せせらぎの里の約40㎡の空き農地で、知り合いの指導を受けて六条大麦の栽培を開始。「昔は収穫時に切り捨てた茎でジュースを飲んでいた」と聞き、海洋ごみになるプラスチック製のストローの代替にしたいと、全国でもまれな大麦ストローを、県内で初めて作り始めました。19年に当産業支援プラザの「起業準備応援助成金」で試作を重ね、20年に販売開始。リサイクルが難しいプラスチック製の「ストローっている?」をもじり、「すとろーている(Straw Tail)」と命名しました。

材料の六条大麦は、クサツパイオニアファーム(草津市)や近江園田ふぁーむ(近江八幡市)からも無償の提供があります。茎が割れないように全て手作業で、刈り取り、乾燥、葉や節のカット、長さの選別、煮沸消毒、仕上げの乾燥と、根気のいる工程が1週間ほど続きます。無農薬なので、かびを防ぐために天候やスピードにも配慮が必要です。実は焙煎して麦茶になります。
実際に大麦ストローを使ってみました。紙ストローに比べ、硬く丈夫で口触りは予想と違い滑らか。耐水性があり長時間使ってもふやけることはありません。薄茶色の自然な風合いがあり、長さや太さの違いも楽しめます。洗浄し乾燥すれば、繰り返して2、3回使うことができ、その後はそのまま花壇やプランターに入れれば自然に生分解して土に返ります。マイストローとして持ち歩けるようにオリジナルの紙製ケースも作り、ネット販売や琵琶湖博物館のショップ販売のほか、飲食店、ノベルティー、エコフェスタなどさまざまな場所で活用されています。

同時に、大麦ストローのワークショップや、プラスチックごみ問題についての出前授業、県立びわ湖フローティングスクールの学習教材の提供など、環境意識を高める活動も進めています。さらに、生ごみの循環利用と削減を目指して段ボールコンポストのアドバイザー資格を取得し、講習会や堆肥の提供も始めました。これらの事業の売り上げの一部は、県内の環境保護活動や国際的な環境保全団体などに寄付しています。
起業から約4年。「『なぜストローの素材が変わったのだろう』と脱プラスチックや地球環境について考え、生態系を見直してもらう糸口になれば」と、自分にできる身近なことから始めた小さな活動は、思いのほか多様な共感を呼び、農業従事者、自然再生に関わる団体、異分野の起業家などとの大きなネットワークが広がっています。
近年、工房シーダーノのように、社会課題の解決を目的とする「ソーシャルベンチャー」が注目を集めています。ボランティアやNPOなどとは異なり、思いをビジネスにする難しさはありますが、「共感」が活力となり、収益を確立することで持続的な成長やさらなるメリットを生む可能性が高まります。1本のストローに込められた強い意思が社会貢献や事業拡大につながるよう、当産業支援プラザは引き続き支援を続けています。
企業概要
工房シーダーノ
(守山市立入町117-7)
https://www.tsuji-pla.co.jp/滋賀県産の無農薬大麦ストローの商品化、脱プラスチックの普及・啓発に向けた講座やワークショップの開催。
お問い合わせ先
(公財)滋賀県産業支援プラザ
情報企画課
- TEL
- 077-511-1411